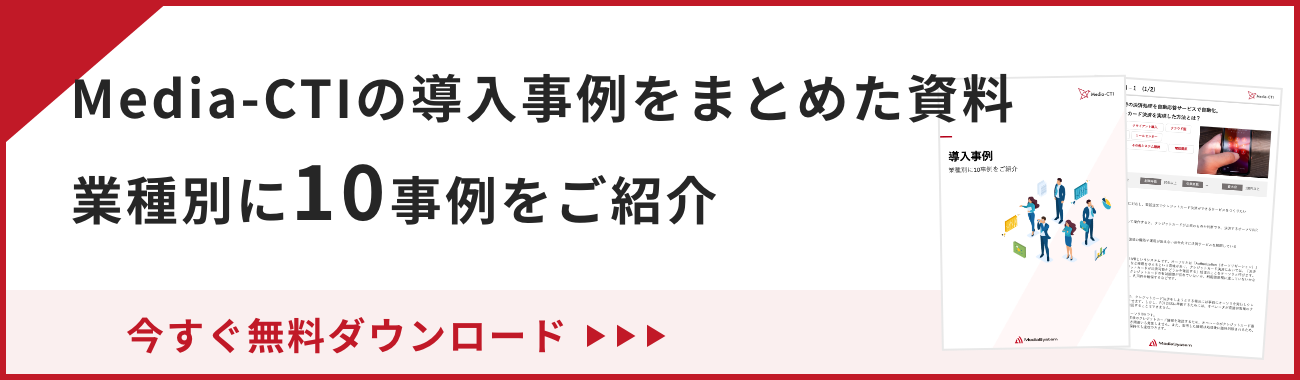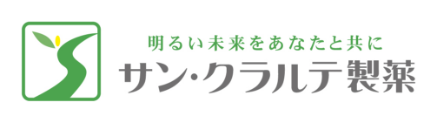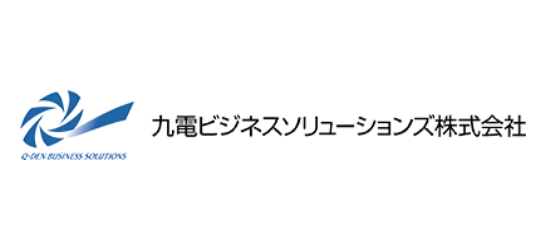自動音声応答で受診予約!受付のダブルブッキング件数を0にしたIVRシステム導入事例
- 医療・製薬
- 自社導入
- クラウド型
- ビジネスフォン
- IVR
- 全通話録音
- 集計レポート
- プレビューダイヤル


療育医療センター
- 創業年数
- 40年以上
- 従業員数
- ー
- 資本金
- ー
導入前の課題
電話で受診予約を受け付けていたが、ダブルブッキングが発生していたので、解消したかった
導入システム
IVRで受診内容を振り分け、全通話録音で予約者確認をおこなう。その日の予約可能件数に達すると自動で予約終了アナウンスに変更される。
導入後の成果
システム上で受信予約を完結するので、予約の重複や聞き漏れなどのミスが発生せず、受付時間や手間が削減された。
電話受付の課題
今回ご紹介する療育医療センターでは、受診予約を電話で受け付けていました。
しかし、予約開始時間になると瞬間的に大量の着信が入るため、重複して受けてしまったり受付に手をとられてしまうことが課題となっていました。
電話受付は、ひと対ひとの会話で手っ取り早い面もあれば、人的ミスを完全に防ぐことが難しいというデメリットがあります。
また人の手がとられてしまうことで、他の業務に支障が出てしまいます。
お互いの負担を解消するために
このように、受診予約が増えるにつれて人員をとられることと予約ミスが発生しており、担当者の負担が増えていました。
また予約する側は、話中で通じなかったり予約ミスが起こることで不満を抱えていました。
そこで解決方法を探っていましたが、受診予約を受け付けるためには、紹介状を持っているかどうか、年齢、名前と電話番号、など確認する項目がいくつかあります。
これまでと変わらず電話で受け付けるためにはどうすれば良いのでしょうか。
IVR(自動音声応答)でできること
一般的によく聞くIVRの音声は「只今、電話が混み合っています」や「〇〇の方は1を~」といった案内です。
音声を聞いて状況を把握するか、案内通り操作して目的を選択するのがIVRの役割です。
人の代わりにシステムが対応してくれるので、人件費削減や時間外対応にも活用されています。
IVRシステムとは
IVRは人のかわりにシステム音声が対応します。
発信者のコールリーズンを振り分けるために利用したり、相手に着信したときに音声を流すこともできます。
主に、「はい・いいえ」や「1・2・3~」など選択できる質問で完結できる会話に適しています。
IVRで受診予約を可能にした方法
1.電話内容を振り分け
今回の事例ではまず、IVRで紹介状の有無や年齢を「はい・いいえ」で振り分ける運用にしました。
ここで注意することは、質問が長いと最後まで聞くまで時間がかかるため、できるだけ短い文章にすることです。
回答を「1・2・3~」とする場合も、回答数が多いと時間がかかるため発信者に不満を与えてしまいます。
そのため、できるだけ少ない回答数に絞る必要があります。
2.通話録音と併用して複雑業務も可能に
次に、予約する方の名前を通話録音で取得します。
通話口で名前を答えてもらい、システム音声で復唱し確認します。
電話番号はプッシュ操作で登録し、予約者情報が登録されます。
通話録音音声をテキスト化
最近は音声認識、音声テキスト化が話題です。
コールセンターなどでも、音声をテキスト化して研修や分析に使いたい、テキストデータを他のツールに連携したいなど、様々な使い方のアイディアが出ています。
弊社でも電話に特化した音声テキスト化を検証中ですが、どの企業も認識率が課題となっています。
特にリアルな音声より電話音声の認識が難しく、音声認識を現場に導入するにはまだ費用対効果が小さいのではないかという状況です。
しかし、電話音声の認識率が向上して実用化が進めば、電話はもっと便利に使えるようになるでしょう。
3.受付件数をリアルタイムで把握
自動音声応答で受診内容を振り分け、通話録音と番号プッシュで予約者の情報を取得できたら、予約管理システムに登録します。
リアルタイムで自動登録するので、予約時間を正確に把握でき、予約一覧から電話番号と通話録音の確認ができます。
受付担当者は空いている時間で折り返し電話をして予約確認をとります。
業務の一部をシステムに頼ること
このように、受付業務を効率化するためシステムを導入し、お互いの負担を解消することができました。
ただし折り返し電話での受付確認は担当者が行っています。
受付時の大量に電話が入ってくる業務だけをシステム化し、最終的な確認は人が対応することで漏れがない運用にしています。
IVRはこうした一次受けをシステム化するのに適しています。
IVRでできないこと
IVRは電話業務を効率化するうえで欠かせないシステムですが、もちろん補えないこともあります。
1.発信者の意思で問い合わせができない
IVRはシステム音声に従って操作する仕組みなので、発信者から自由な問い合わせをすることができません。
クレームや緊急の問い合わせは温度感が上がってしまう可能性があります。
2.すぐに回答できない
IVRは回答の選択肢を全て聞いてから番号プッシュで応答するため、特に初めて発信した時はどの選択肢があるか確認しなければならず、ストレスを感じさせることがあります。
そのため、質問を短くしたり選択肢を少なくするなど工夫が必要です。
3.決められた答えしか得られない
IVRは今回のように回答者の数が少ない、かつ名前のような短い回答であれば通話録音での回答取得が可能ですが、複雑な回答は難しい仕組みです。
自動音声応答の今後
IVRは、電話の一次受けなど業務効率化で欠かせない存在です。
しかし最近は、音声認識やAI技術が進歩したことでAIボイスボットなどが注目されています。
IVRでカバーできなかった、人同士のような複雑な会話をすることが可能になり、システム化できる範囲が広がっています。
今後はIVRとボイスボットを業務によって使い分けるなど選択肢が増え、ますます便利になっています。